【麻雀用語】初心者が覚えるべき基本用語を全て解説
最終更新:
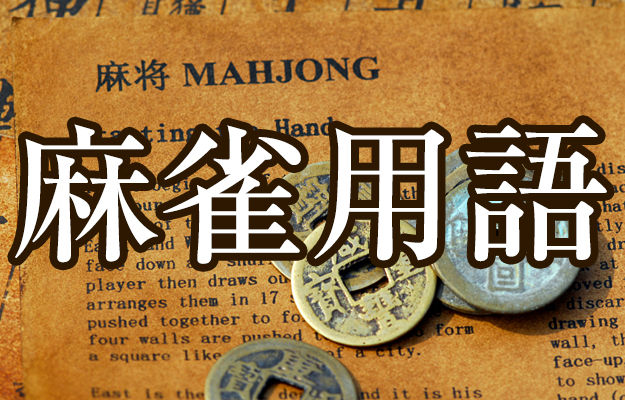
麻雀ゲームで遊んでいる時、麻雀漫画を読んだり麻雀アニメを観ている時に意味が分からない麻雀用語が出てくることがありませんか?
ここでは、麻雀を楽しむ上で覚えておきたい麻雀用語をご紹介!
友人と麻雀をプレイしている最中、麻雀用語を使っている人がいると中級者っぽく見えますよね。強く見えると相手にプレッシャーを与えることもできるかも?!
麻雀用語一覧
ゲーム単位の用語
- 局(キョク)
- 麻雀ゲームの試合単位。配牌 から アガる 勝者が出るまで、或いは、誰も アガら ない 流局 までが 1局。麻雀用語辞典
- 流局(リュウキョク)
- 麻雀ゲームで誰も アガり がなく 局 が終了すること。流れる などとも言う。
麻雀用語辞典へ
- 半荘(ハンチャン)
- 麻雀ゲームの試合単位。前半戦の東場(トンバ) と 後半戦の南場(ナンバ) で東4局、南4局の全8局。
麻雀用語辞典へ
- 一荘(イーチャン)
- 麻雀ゲームの試合単位。東場(トンバ)・南場(ナンバ)・西場(シャーバ)・北場(ペーバ)で各4局の全16局。
麻雀用語辞典へ
- 東風戦(トンプウセン)
- 麻雀ゲームの試合単位。1回親が回る 東場(トンバ) の全4局、或いは、東場で終了するゲーム方法。
麻雀用語辞典へ
- 南風戦(ナンプウセン)
- 麻雀ゲームの試合単位。東場(トンバ) の後の2周目となる 南場(ナンバ) の全4局。
麻雀用語辞典へ
- 西風戦(シャープウセン)
- 麻雀ゲームの試合単位。南場(ナンバ) の後の3周目となる 西場(シャーバ) の全4局。半荘戦の延長や一荘戦で行われる。
麻雀用語辞典へ
- 北風戦(ペープウセン)
- 麻雀ゲームの試合単位。西場(シャーバ) の後の4周目となる 北場(ペーバ) の全4局。半荘戦の延長や一荘戦で行われる。
麻雀用語辞典へ
- オーラス
- ゲームの最後の1局を示す。半荘(ハンチャン)戦の場合は南4局目のこと。
麻雀用語辞典へ
- ラス前
- オーラスの前の 局。最後の局の前の1局。
麻雀用語辞典へ
場の用語
- 場(バ)
- 起家(チーチャ)から始まり4人プレイヤーの全員が左回りで1度親になる1周のこと。
麻雀用語辞典へ
- 東場(トンバ)
- 起家(チーチャ)から始まり4人プレイヤーの全員が左回りで1度親になる最初の1周。半荘(ハンチャン) の前半戦。
麻雀用語辞典へ
- 南場(ナンバ)
- 起家(チーチャ)から始まり4人プレイヤーの全員が左回りで1度親になる2回目の1周。半荘(ハンチャン) の後半戦。
麻雀用語辞典へ
- 西場(シャーバ)
- 起家(チーチャ)から始まり4人プレイヤーの全員が左回りで1度親になる3回目の1周。一半荘(イーチャン) の西場。
麻雀用語辞典へ
- 北場(ペーバ)
- 東家(トンチャ)から始まり4人プレイヤーの全員が左回りで1度親になる4回目の1周。一半荘(イーチャン)の北場。
麻雀用語辞典へ
- 本場(ホンバ)
- 親が 連荘 か ノーテン で 流局 した場合に 本場 が増える。子 が アガる と0本場に戻る。例:東1局2本場(東場 の最初の 局 で親が3回 続いている状態)
麻雀用語辞典へ
- 荒れ場(アレバ)
- 大きな アガり役 で高い点数のやり取りが続く 場 の状況のこと。
麻雀用語辞典へ
- 小場(コバ)
- 小さな アガり役 で安い点数のやり取りが続く 場 の状況のこと。
麻雀用語辞典へ
- 積み棒(ツミボウ)
- 親 が 連荘(レンチャン) している目印として卓上に置く100点棒のこと。
麻雀用語辞典へ
- 南入(ナンニュウ)
- 場が 南場(ナンバ) に入ること。
麻雀用語辞典へ
- 西入(シャーニュウ)
- 場が 西場(シャーバ) に入ること。
麻雀用語辞典へ
- 北入(ペーニュウ)
- 場が 北場(ペーバ) に入ること。
麻雀用語辞典へ
- 平場(ヒラバ)
- 親が1回目で 積み棒 が1本もない 局 のこと。
麻雀用語辞典へ
- 一本場(イッポンバ)
- 現在、親 の 連荘(レンチャン) 或いは、流局(リュウキョク) によって 積み棒 を一本卓上に出した状態。
麻雀用語辞典へ
- 連荘(レンチャン)
- 同じ 局 で同じプレイヤーが親を連続して続けること。
麻雀用語辞典へ
- 河(ホー)
- 捨牌 を並べる 山牌 に囲まれた卓上の中央部分の場所
麻雀用語辞典へ
- 開門(カイメン)
- 配牌 時に親のサイコロの出目に従って 牌山 を切り開くこと。
麻雀用語辞典へ
- 東発(トンパツ)
- 東1局のことを東発(とんぱつ)と呼びます。麻雀では、一番初めに親を決めて東1局がスタートします。
麻雀用語辞典へ
プレイヤー名称の用語
- 親(オヤ)
- 現在の 局 における 東家(トンチャ) のこと。
麻雀用語辞典へ
- 子(コ)
- 親 以外の 南家(ナンチャ) 西家(シャーチャ) 北家(ペーチャ) のこと。
麻雀用語辞典へ
- 起家(チーチャ)
- 半荘(ハンチャン) で 東1局 の最初の親など対局開始時の最初の親のこと。
麻雀用語辞典へ
- 東家(トンチャ)
- 現在の 局 の親のこと。
麻雀用語辞典へ
- 南家(ナンチャ)
- 現在の 局 の親の 東家(トンチャ) から見て右の人。
麻雀用語辞典へ
- 西家(シャーチャ)
- 現在の 局 の親の 東家(トンチャ) から見て正面の人。
麻雀用語辞典へ
- 北家(ペーチャ)
- 現在の 局 の親の 東家(トンチャ) から見て左の人。
麻雀用語辞典へ
- 上家(カミチャ)
- 自分から見て左隣の人
麻雀用語辞典へ
- 下家(シモチャ)
- 自分から見て右隣の人
麻雀用語辞典へ
- 対面(トイメン)
- 自分から見て正面の人
麻雀用語辞典へ
- 仮東(カリトン)
- ゲーム開始時、プレイヤーの場所を決める際、東の牌を取った人が座る位置。
麻雀用語辞典へ
- 仮親(カリオヤ)
- ゲーム開始時、プレイヤーの場所を決める際、仮東(カリトン)が振ったサイコロの目の位置に座るプレイヤー。
麻雀用語辞典へ
ゲームルールの用語
- 頭ハネ(アタマハネ)
- あるプレイヤーの 打牌(ダハイ) に対して2人以上が同時に ロン を宣言した場合、打牌 した人から反時計回りで最も近いプレイヤーに アガる 優先順位があるルール。
麻雀用語辞典へ
- 当たり牌(アタリハイ)
- ロン できる牌。アガり が宣言できる牌。
麻雀用語辞典へ
- アリアリ
- 鳴いてタンヤオを認める喰いタン、鳴き(副露:フーロ)の後に役牌で刻子(コーツ)や槓子(カンツ)を作ることで役付を有効とする後付けこれら両方を認めるルール。
麻雀用語辞典へ
- アリナシ
- 鳴いてタンヤオを認める喰いタン、鳴き(副露:フーロ)の後に役牌で刻子(コーツ)や槓子(カンツ)を作ることで役付を有効とする後付けどちらか一方を認めるルール。
麻雀用語辞典へ
- アリス
- メンゼン 或いは 立直(リーチ) で 和了(ホーラ=アガり)した場合、ドラ表示牌 の隣の牌を捲り、手牌に同じ種類の牌があればチップを貰えるルール。
麻雀用語辞典へ
- 九種九牌(キュウシュキュウハイ)
- 配牌時の第一ツモの時点で、手牌に一九字牌が九種類以上含まれている状態。または、その状態で流局を宣言できるルール。ただし、宣言前に鳴きが入ると無効。
麻雀3分講座へ
- 四風連打(スーフーレンダ)
- 全プレイヤーの最初の 捨牌 が同じ 風牌 だった場合に 流局 となる。
麻雀用語辞典へ
- 四風子連打(スーフォンツリェンター)
- 全プレイヤーの最初の 捨牌 が同じ 風牌 だった場合に 流局 となる。
麻雀用語辞典へ
- 四家同風(スーチャトンフォン)
- 全プレイヤーの最初の 捨牌 が同じ 風牌 だった場合に 流局 となる。
麻雀用語辞典へ
点数系の用語
- 翻(ファン、ハン)
- 手役の種類 や ドラの枚数 によって点数を数える場合の単位。
麻雀用語辞典へ
- 符(フ)
- 待ち の種類や 面子(メンツ) の種類によって点数を計算する場合の単位。
麻雀用語辞典へ
- 副底(フーテイ)
- アガる ことで必ず付与される20符。符底とも言う。
麻雀用語辞典へ
- 満貫(マンガン)
- アガり役 が 5翻 の場合に付与される点数。親の場合12,000点、子の場合8,000点。
麻雀用語辞典へ
- 跳満(ハネマン)
- アガり役 が 6、7翻 の場合に付与される点数。満貫 の1.5倍の点数。親の場合18,000点、子の場合12,000点。
麻雀用語辞典へ
- 倍満(バイマン)
- アガり役 が 8、9、10翻 の場合に付与される点数。満貫 の2倍の点数。親の場合24,000点、子の場合16,000点。
麻雀用語辞典へ
- 三倍満(サンバイマン)
- アガり役 が 11、12翻 の場合に付与される点数。満貫 の3倍の点数。親の場合36,000点、子の場合24,000点。
麻雀用語辞典へ
- 数え役満(カゾエヤクマン)
- アガり役 が 13翻以上 の場合に付与される点数。満貫 の4倍の点数。親の場合48,000点、子の場合32,000点。
麻雀用語辞典へ
- 役満(ヤクマン)
- 最高の点数の アガり役。親の場合48,000点、子の場合32,000点。
麻雀用語辞典へ
- 点棒(テンボウ)
- 麻雀ゲームで使用する点数が記載された棒。勝ちや負けに応じてプレイヤー同士でやり取りする。100点棒、1,000点棒、5,000点棒、10,000点棒と4種類ある。
麻雀用語辞典へ
- 立直棒(リーチボウ)
- 立直(リーチ)を掛ける際に卓上に出す供託用の1,000点棒。
麻雀用語辞典へ
- 点箱(テンバコ)
- 点棒を入れるのに使用する箱のこと。
麻雀用語辞典へ
- 箱点(ハコテン)
- 手持ちの点数が0になること。=ハコる、飛び、ハコ などとも言う。
麻雀用語辞典へ
- 青天井(アオテンジョウ)
- 点数計算のルール。通常、点数計算は満貫(マンガン)以上から翻数により点数を加算しますが、青天井の場合は満貫以上でも正式な点数計算を行います。結果、非常に高い点数になることがあります。
麻雀用語辞典へ
牌系の用語
- 牌(パイ)
- ゲームで使用する図柄の異なる駒。牌は字牌(ツーパイ)7種、数牌(シュウパイ)27種の合計34種で各4枚あるので全部で136枚ある。
麻雀用語辞典へ
- 配牌(ハイパイ)
- 各 局 の最初で4人のプレイヤーに牌を配ること。親が14枚 で 子が13枚 ある。
麻雀用語辞典へ
- 手牌(テハイ)
- ゲーム進行中に常に自分の手元にある 牌。通常 親14枚 子13枚 ある。
麻雀用語辞典へ
- 王牌(ワンパイ)
- 各 局 の 配牌 時に 牌山 の最後に残す2段7列の14枚の牌。王牌 はツモれないが、カン の時に 配牌 する嶺上牌(リンシャンハイ) は例外。
麻雀用語辞典へ
- 牌山(ハイヤマ)
- 各 局 のゲーム開始時、各プレイヤーが2段17枚で積んだ卓上の牌のこと。
麻雀用語辞典へ
- 壁牌(ピーパイ)
- 各 局 のゲーム開始時、各プレイヤーが2段17枚で積んだ卓上の牌のこと。牌山 とも言います。王牌(ワンパイ) を除く。
麻雀用語辞典へ
- 洗牌(シーパイ)
- 各 局 のゲーム開始時、牌 をプレイヤー全員で良く混ぜる行為。
麻雀用語辞典へ
- 多牌(ターハイ)
- 手牌 が13枚より多くなっている状態。その 局 で アガる ことはできない。
麻雀用語辞典へ
- 少牌(ショウハイ)
- 手牌 が13枚より少なくなっている状態。その 局 で アガる ことはできない。
麻雀用語辞典へ
- 理牌(リーパイ)
- 手牌 の牌を同じ種類や順番に並べ替えること。
麻雀用語辞典へ
- 安全牌(アンゼンパイ)
- 他のプレイヤーの 和り(アガり)牌 にならない安全な牌。安牌(アンパイ)とも言う。
麻雀用語辞典へ
- 危険牌(キケンハイ)
- 他のプレイヤーの 和り(アガり)牌 になる可能性の高い危険な牌。
麻雀用語辞典へ
- アガリ牌
- アガリ形 を完成させる最後の牌。ロン や ツモ で アガッた牌。
麻雀用語辞典へ
- 花牌(ファパイ/ハナハイ)
- 図柄に四季が描かれた特殊な牌で中国麻雀で使用する。
麻雀用語辞典へ
- 風牌(フォンパイ/カゼハイ)
- 牌 の中の 東(トン)・南(ナン)・西(シャー)・北(ペー) の 牌。風牌(カゼハイ/フォンパイ) とも言う。
麻雀用語辞典へ
- 字牌(ツーパイ)
- 牌 の中の漢字で書かれた図柄の牌と何も図柄がない牌。風牌(フォンパイ)の 東西南北(トンナンシャーペー) の4種と 白發中(ハクハツチュン) の 三元牌(サンゲンパイ) の3種の合計7種。
麻雀用語辞典へ
- 数牌(シュウパイ)
- 牌 の中の数字で書かれた図柄の牌。筒子(ピンズ)・索子(ソーズ)・萬子(ワンズ)の3種が数字の1~9まで用意されている。
麻雀用語辞典へ
- 三元牌(サンゲンパイ)
- 字牌(ツーパイ) の中の 白・發・中(ハク・ハツ・チュン) の総称。
麻雀用語辞典へ
- 中張牌(チュンチャンパイ)
- 数牌(シュウパイ) の中の 2 ~ 8 までの牌の総称。
麻雀用語辞典へ
- 尖張牌(センチャンパイ)
- 数牌(シュウパイ) の中の 3 と 7 であり、端から3番目の牌の総称。ペンチャン待ち専用の牌となる。
麻雀用語辞典へ
- 老頭牌(ロートーハイ)
- 数牌(シュウパイ) の 1 と 9 の牌の総称。
麻雀用語辞典へ
- 幺九牌(ヤオチュウハイ)
- 数牌(シュウパイ) の 1 と 9 と 字牌(ツーパイ) の牌の 総称。
麻雀用語辞典へ
- 筒子(ピンズ)
- 丸い玉の図柄の描かれた 数牌(シュウパイ)で一筒から九筒までの9種類の牌の総称。
麻雀用語辞典へ
- 萬子(ワンズ/マンズ)
- 漢数字に 萬 の図柄の描かれた 数牌(シュウパイ)で一萬から九萬までの9種類の牌の総称。
麻雀用語辞典へ
- 索子(ソーズ)
- 細長い竹のような図柄の描かれた 数牌(シュウパイ)で一索から九索までの9種類の牌の総称。※一索は鳥の図柄。
麻雀用語辞典へ
- 嶺上牌(リンシャンハイ)
- 牌山(ハイヤマ) を 開門(カイメン) した際、王牌(ワンパイ) の内、ドラ表示牌 の隣の最後の4枚。カン の時に 配牌 する 牌。
麻雀用語辞典へ
- 海底牌(ハイテイハイ)
- 壁牌(ピーパイ) の最後の1枚。
麻雀用語辞典へ
- 河底牌(ホウテイハイ)
- 最後の 海底牌(ハイテイハイ) を取得した人が 打牌 した 最後の 捨牌。
麻雀用語辞典へ
- オタ風(オタカゼ)
- 場風(バカゼ) や 門風(メンフォン) でない 風牌(フォンパイ) のこと。
麻雀用語辞典へ
- オタ風牌(オタカゼハイ)
- 場風(バカゼ) や 門風(メンフォン) でない 風牌(フォンパイ) のこと。
麻雀用語辞典へ
- 客風牌(コーフォンパイ)
- 場風(バカゼ) や 門風(メンフォン) でない 風牌(フォンパイ) のこと。
麻雀用語辞典へ
- 場風(バカゼ)
- 現在の 局 における場と同じ 風牌(フォンパイ) のこと。東場なら字牌の東、南場なら字牌の南のこと。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 場風牌(バカゼハイ)
- 現在の 局 における場と同じ 風牌(フォンパイ) のこと。東場なら字牌の東、南場なら字牌の南のこと。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 圏風牌(チャンフォンパイ)
- 現在の 局 における場と同じ 風牌(フォンパイ) のこと。東場なら字牌の東、南場なら字牌の南のこと。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 荘風牌(チャンフォンパイ)
- 現在の 局 における場と同じ 風牌(フォンパイ) のこと。東場なら字牌の東、南場なら字牌の南のこと。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 自風(ジカゼ)
- 現在の 局 における自分の 風牌(フォンパイ) のこと。東家(トンチャ) は字牌の東、南家(ナンチャ) は字牌の南。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 門風(メンフォン)
- 現在の 局 における自分の 風牌(フォンパイ) のこと。東家(トンチャ) は字牌の東、南家(ナンチャ) は字牌の南。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 自風牌(ジカゼハイ)
- 現在の 局 における自分の 風牌(フォンパイ) のこと。東家(トンチャ) は字牌の東、南家(ナンチャ) は字牌の南。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 門風牌(メンフォンパイ)
- 現在の 局 における自分の 風牌(フォンパイ) のこと。東家(トンチャ) は字牌の東、南家(ナンチャ) は字牌の南。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 翻牌(ファンパイ)
- 刻子(コーツ) や 槓子(カンツ) を作ると 翻(ファン) が付く 役牌(ヤクハイ)のこと。三元牌(サンゲンパイ)、門風牌(メンフォンパイ)、圏風牌(チャンフォンパイ)など。
麻雀用語辞典へ
- 連風牌(リェンフォンパイ/レンフォンパイ)
- 圏風牌(チャンフォンパイ) でかつ 門風牌(メンフォンパイ) でもある牌のこと。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- ダブ東(ダブトン)
- 東場(トンバ) の 東家(トンチャ) の状態で東の 刻子(コーツ) を作ると2翻付く。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- ダブ南(ダブナン)
- 南場(ナンバ) の 南家(ナンチャ) の状態で南の 刻子(コーツ) を作ると2翻付く。役牌の1種。
麻雀用語辞典へ
- 孤立牌(コリツハイ)
- 手牌の中で孤立している種類の牌で、対子(トイツ)、塔子(ターツ)、順子(シュンツ)、刻子(コーツ) の何れにもなっていない牌。
麻雀用語辞典へ
ドラ系用語
- ドラ
- アガった場合に、 ドラ を持っていれば1枚で1翻(イッパン/イーファン)加算される特別な牌。一般的に 懸賞牌 とも言う。役 は付かない。
麻雀用語辞典へ
- ドラ表示牌
- ドラ がどの種類の牌であるか示す牌。ドラ表示牌 の次の牌が ドラ となる。例えば筒子の2がドラ表示牌であれば、ドラは筒子の3となる。
麻雀用語辞典へ
- 裏ドラ(ウラドラ)
- 立直(リーチ) をかけて アガッた場合に、ドラ表示牌 の真下に位置する牌も ドラ表示牌 となるルール。
麻雀用語辞典へ
- 槓ドラ(カンドラ)
- プレイヤーが カン した場合に、 ドラ表示牌 の隣の牌を開き ドラ表示牌 が追加されるルール。最大4つまで増える。
麻雀用語辞典へ
- 槓ウラ(カンウラ)
- 槓ドラが追加されている際、立直(リーチ) をかけて アガッた場合に、槓ドラ表示牌 の真下に位置する牌も ドラ表示牌 となるルール。
麻雀用語辞典へ
- 赤牌(アカハイ)
- 手牌 にあるだけで ドラ 扱いとなる特別な牌。一般的には 5萬・5筒・5索 が赤い図柄で描かれている。
麻雀用語辞典へ
ツモと捨て牌
- 自摸(ツモ)
- 局 の最初に作った 牌山 からプレイヤーが順番に牌を1枚取る行為。
麻雀用語辞典へ
- 打牌(ダハイ)
- 自摸(ツモ) や ポン・チー・カン などの後に、牌を1枚 河(ホー) に 捨てる/切る 行為。
麻雀用語辞典へ
- 捨牌(ステハイ)
- 打牌(ダハイ) によって捨てられた 牌、又は、その牌が並べられた 河(ホー)にある牌のこと。
麻雀用語辞典へ
- ツモ切り(ツモギリ)
- 牌山 から 自摸(ツモ) した牌を 手牌 に混ぜないでそのまま捨てる行為。
麻雀用語辞典へ
鳴き用語
- ポン
- 手牌に2枚同じ種類の牌が揃っている 対子(トイツ) がある状態で、 他家(ターチャ) が切った牌を貰って3枚の 刻子(コーツ) を作る行為。鳴きで作成した刻子は場に晒す。
麻雀用語辞典へ
- チー
- 手牌に2枚連続した 数牌(シュウパイ)の 塔子(ターツ) がある状態で、 上家(カミチャ) が切った牌を貰って3枚の 順子(シュンツ) を作る行為。鳴きで作成した順子は場に晒す。
麻雀用語辞典へ
- 明カン(ミンカン)
- 3枚同じ種類の牌がある 刻子(コーツ) の状態で 他家(ターチャ) が切った牌を貰って4枚の 槓子(カンツ) を作る行為。鳴きで作成した槓子は場に晒す。
麻雀用語辞典へ
- 暗カン(アンカン)
- 3枚同じ種類の牌がある 刻子(コーツ) の状態で 自分のツモ牌を利用して4枚の 槓子(カンツ) を作る行為。作成した槓子は場に晒す。
麻雀用語辞典へ
- 空ポン(クウポン)
- 1度宣言した ポン を取りやめること。
麻雀用語辞典へ
- 空チー(クウチー)
- 1度宣言した チー を取りやめること。
麻雀用語辞典へ
- 空カン(クウカン)
- 1度宣言した カン を取りやめること。
麻雀用語辞典へ
- 誤ポン(ゴポン)
- 誤った ポン を行う行為。
麻雀用語辞典へ
- 誤チー(ゴチー)
- 誤った チー を行う行為。
麻雀用語辞典へ
- 誤カン(ゴカン)
- 誤った カン を行う行為。
麻雀用語辞典へ
- 副露(フーロ)
- 他家 の 捨牌 を ポン、チー、明カン などして取得することで面子(メンツ)を揃えること。
麻雀用語辞典へ
- 鳴く(晒す、叩く)
- 他家 の 捨牌 を ポン、チー、明カン などして取得することで面子(メンツ)を揃えること。
麻雀用語辞典へ
- ポン材(ポンザイ)
- ポンをするための素材・材料となる対子(といつ)のこと。
麻雀用語辞典へ
- ポン聴(ポンテン)
- ポンを宣言して取得した牌でテンパイの状態になること。
麻雀用語辞典へ
メンゼン/食い系用語
- メンゼン役
- ポン、チー、明カン などせず、ツモ で 面子(メンツ) を全て揃えて アガる 役。
麻雀用語辞典へ
- 門前(メンゼン)
- 他家(ターチャ) の 捨牌 で ポン、チー、明カン などによる 鳴き(副露:フーロ) をせず、ツモ によって自力で手牌を揃えること。
麻雀用語辞典へ
- 喰い下がり(クイサガリ)
- 他家(ターチャ) の 捨牌 で ポン、チー、明カン などして 鳴き(副露:フーロ) によって1翻(イーファン)下がること。
麻雀用語辞典へ
- 喰い制限なし(クイセイゲンナシ)
- 他家(ターチャ) の 捨牌 で ポン、チー、明カン などして 鳴き(副露:フーロ) をしても 役 が成立すること。
麻雀用語辞典へ
- 喰いタン
- 他家(ターチャ) の 捨牌 で ポン、チー、明カン などして 鳴き(副露:フーロ) ながら タンヤオ を揃えること。
麻雀用語辞典へ
牌の組み合わせに関する用語=面子(メンツ)
- 頭(アタマ)
- 雀頭(ジャントウ)といって アガりの形 の中で同じ種類の牌2枚1組で作る組み合わせ。
麻雀用語辞典へ
- 面子(メンツ)
- 和り(アガり) の形を整える際に揃える牌の組み合わせ。順子(シュンツ)、刻子(コーツ)、槓子(カンツ)のこと。
麻雀用語辞典へ
- 塔子(ターツ)
- [12] や[56] や[79]など2枚の 数牌(シュウパイ) の組み合わせ。後1枚で 順子(シュンツ) になる状態。
麻雀用語辞典へ
- 対子(トイツ)
- [22] や [77] など2枚同じ種類の牌の組み合わせ。後1枚で 刻子(コーツ) になる状態。
麻雀用語辞典へ
- 順子(シュンツ)
- [123] や [567] など3枚連続した数牌(シュウパイ) を揃えた面子
麻雀用語辞典へ
- 刻子(コーツ)
- [222] や [東東東] など3枚同じ種類の牌を揃えた面子
麻雀用語辞典へ
- 槓子(カンツ)
- [2222] や [東東東東] など4枚同じ種類の牌を揃えた面子。
麻雀用語辞典へ
- 暗刻(アンコ)
- 鳴かずに3枚同じ種類の牌を揃えた面子。
麻雀用語辞典へ
- 明刻(ミンコ)
- 鳴き(副露:フーロ) で 3枚同じ種類の牌を揃えた面子。
麻雀用語辞典へ
- 暗槓(アンカン)
- 鳴かずに4枚同じ種類の牌を揃えた面子。
麻雀用語辞典へ
- 明槓(ミンカン)
- 鳴き(副露:フーロ) で4枚同じ種類の牌を揃えた面子=大明槓(ダイミンカン)とも言う。
麻雀用語辞典へ
- 加槓(カカン)
- ポン している状態で 同じ種類の牌を 自摸(ツモ) った場合に、その牌を加えて4枚揃えた面子=小明槓(ミンカン)とも言う。
麻雀用語辞典へ
- ダブル面子(ダブルメンツ)
- 連続する2つの対子(トイツ)が組み合わさった状態のこと。
麻雀用語辞典へ
アガり系用語
- 和了(ホーラ)
- 決められたルールに従って揃えた 手牌 を ツモ か ロン を宣言して全員に見せること=和り(アガり)。なんの問題もなければ和了(ホーラ)が確定する。
麻雀用語辞典へ
- 和り(アガり)
- 決められたルールに従って揃えた 手牌 を ツモ か ロン を宣言して全員に見せること=和了(ホーラ)。なんの問題もなければ和了(ホーラ)が確定する。
麻雀用語辞典へ
- 和る(アガる)
- 決められたルールに従って揃えた 手牌 を ツモ か ロン を宣言して全員に見せること=和了(ホーラ)。なんの問題もなければ和了(ホーラ)が確定する。
麻雀用語辞典へ
- 和了る(アガる)
- 決められたルールに従って揃えた 手牌 を ツモ か ロン を宣言して全員に見せること=和了(ホーラ)。なんの問題もなければ和了(ホーラ)が確定する。
麻雀用語辞典へ
- アガラス
- 最終局(オーラス)で和了ったにもかかわらず「最下位=ラス」の状態で終了してしまった状態。ラスの状態のまま東風戦(トンプウセン)や半荘(ハンチャン)など、ゲームを終了させてしまう和了のこと。
麻雀用語辞典へ
- 和了癖(アガリグセ)
- なかなか和了ることが出来ない場合に、アガりの成功例を1つでも作って調子や流れを変えたい場合に和了癖(アガリグセ)を付けると言う。和了癖を付ける場合は食いタンなど安くて早い手で和了を目指すことが多い。
麻雀用語辞典へ
- 和了トップ(アガリトップ)
- 最終局(オーラス)で和了することが出来れば1位のトップの状態でゲームを終了できるプレイヤーに対して言う。
麻雀用語辞典へ
- 和了逃し(アガリノガシ)
- 和了(ホーラ)出来ていたはずの手において、自分のミスによって和了りを逃してしまうこと。
麻雀用語辞典へ
- 和了牌(アガリハイ)
- ロン牌やツモ牌のこと。和了った場合に最後の待ち牌のことを和了牌と言う。リャンメン待ちなど複数の待ち牌がある場合はすべて和了牌となる。
麻雀用語辞典へ
- 和了放棄(アガリホウキ)
- ゲーム中に違反行為(=チョンボ)を犯してしまうことで和了することが出来ない状態。ペナルティーのこと。
麻雀用語辞典へ
- 和了目(アガリメ)
- 和了できるかどうかの可能性を示す言葉。和了目があるとする場合は和了できる可能性がある状態で、和了目がないとする場合は和了できる可能性がない状態。
麻雀用語辞典へ
- 和了役(アガリヤク)
- 和了した時の手役のこと。
麻雀用語辞典へ
- 和了連荘(アガリレンチャン)
- 親が和了した場合には連荘(レンチャン=親の連続)が可能で、テンパイでは親が流れてしまうというルール。
麻雀用語辞典へ
- 和り形(アガリケイ)
- アガる のに必要となる 手牌の形。アガった 時に揃えられている 待ちの種類 や 役 などの形。
麻雀用語辞典へ
- 和了形(ホーラケイ)
- アガる のに必要となる 手牌の形。アガった 時に揃えられている 待ちの種類 や 役 などの形。
麻雀用語辞典へ
- ロン
- 他家 の 捨牌 で アガリ形 を完成させ、アガり を宣言して 手牌 へ行為。=直撃、直取り などとも言う。
麻雀用語辞典へ
- 栄和(ロンホー)
- 他家 の 捨牌 で アガリ形 を完成させ、アガり を宣言して 手牌 へ行為。=直撃、直取り などとも言う。
麻雀用語辞典へ
- 自模和(ツモホー)
- 自摸(ツモ)によって、アガリ形を完成させ、アガりを宣言して手牌へ行為。
麻雀用語辞典へ
- 門前清自摸和(メンゼンツモ)
- 自摸(ツモ) によって、 アガリ形 を完成させ、アガり を宣言して 手牌 へ行為。=メンゼンツモ
麻雀用語辞典へ - 一発(イッパツ)
- 立直(リーチ) をかけてから 1巡内 に ツモ や ロン で アガる こと。アガる 前に ポン・チー・カン されると無効となる。
麻雀用語辞典へ - 手役(テヤク)
- アガり役 や 手牌 の 役 のこと。
麻雀用語辞典へ - 振り込み
- 自分の 打牌 に対して 他家 が ロン して アガられてしまうこと。
麻雀用語辞典へ - 放銃(ホウジュウ)
- 自分の 打牌 に対して 他家 が ロン して アガられてしまうこと。
麻雀用語辞典へ - 嵌張待ち(カンチャンマチ)
- テンパイ の際、例えば完成していない最後の面子(メンツ)が[ 1・3 ]であり、真ん中の数字がない状態で、真ん中の数字の牌が来れば、順子(シュンツ)が完成し和了(ホーラ=アガり)となる1枚の待ちの形。
麻雀用語辞典へ - 辺張待ち(ペンチャンマチ)
- テンパイ の際、例えば完成していない最後の面子(メンツ)が[ 1・2 ]であり、端の数字がない状態で、端の数字の牌が来れば、順子(シュンツ) が完成し和了(ホーラ=アガり)となる1枚の待ちの形。
麻雀用語辞典へ - 両面待ち(リャンメンマチ)
- テンパイ の際、例えば完成していない最後の面子(メンツ)が[ 3・4 ]であり、両面塔子(リャンメンターツ)の状態で、両端のどちらの牌が来ても順子(シュンツ)が完成し和了(ホーラ=アガり)となる2枚の待ちの形。
麻雀用語辞典へ - 単騎待ち(タンキマチ)
- テンパイ の際、すべての面子(メンツ)が完成しているが、アタマ が1枚しかなく、もう1枚来れば 対子(トイツ) が完成し和了(ホーラ=アガり)となる1枚待ちの形。最後の1枚を単騎待ちする場合は地獄単騎などとも言う。
麻雀用語辞典へ - 双碰待ち(シャンポンマチ)
- テンパイ の際、例えば完成していない最後の面子(メンツ)が[ 3・3・中・中 ]とあり、待ちの形が対子(トイツ)2組ある状態で、どちらか一方の種類の牌が来れば、一方が アタマ となり、一方が 刻子(コーツ)となり 和了(ホーラ=アガり)する2枚の待ちの形。
麻雀用語辞典へ - ノベタン
- テンパイ の際、アタマ が1枚しかなく、例えば手牌に[ 2・3・4・5 ]とあり、 2 か 5 のどちらか一方が来れば 対子(トイツ) となり アタマ が完成し 和了(ホーラ=アガり) する 2枚待ちの形。
麻雀用語辞典へ - 裸単騎(ハダカタンキ)
- ポン、チー、カン、などによってすべての 面子(メンツ) を晒している状態で アタマ の残り1枚を待っている状態。
麻雀用語辞典へ - 一向聴(イーシャンテン)
- 残り1枚必要な牌が 手牌 に加われば 聴牌(テンパイ)となる状態。
麻雀用語辞典へ - 二向聴(リャンシャンテン)
- 残り2枚必要な牌が 手牌 に加われば 聴牌(テンパイ)となる状態。
麻雀用語辞典へ - 聴牌(テンパイ)
- 残り1枚必要な牌が 手牌 に加われば 和り(アガリ) となる状態。
麻雀用語辞典へ - 不聴(ノーテン)
- 面子(メンツ) や アタマ が揃っていない、テンパイ していない状態。
麻雀用語辞典へ - 不聴罰符(ノーテンバップ)
- 誰も アガり なしで 局 が終了した場合、 ノーテン のプレイヤーが テンパイ のプレイヤーに点数を支払うこと。通常 場 に3,000点あるものと計算する。
麻雀用語辞典へ - 立直(リーチ)
- テンパイ 状態で 立直 と宣言して1,000点棒を 場 に出すことで付く アガり役。門前(メンゼン)が条件。
麻雀用語辞典へ - 即リー(ソクリー)
- テンパイ したら即 立直 をかけること。
麻雀用語辞典へ - ダブルリーチ
- 1巡目に 立直 を宣言することで2翻役が成立する アガり役。
麻雀用語辞典へ - 足止め立直(アシドメリーチ)
- 他家(ターチャ)を牽制し、聴牌(テンパイ) を遅らせたり崩させたりするための 安手 や 愚形 の 立直。
麻雀用語辞典へ - 黙聴(ダマテン)
- 門前(メンゼン)で テンパイ している状態で 立直 せずに黙っている状態。
麻雀用語辞典へ - 闇聴(ヤミテン)
- 門前(メンゼン)で テンパイ している状態で 立直 せずに黙っている状態。
麻雀用語辞典へ - 振聴(フリテン)
- 自分の アガり牌 が 自分の 捨牌 の中にある状態や、立直後に他家(ターチャ) が 打牌 した アガり牌 を見逃してしまった状態。
麻雀用語辞典へ - 同巡内振聴(ドウジュンナイフリテン)
- テンパイ の状態で 他家(ターチャ) が 打牌 した アガり牌 を見逃してしまった後、自分のツモ巡が来ていない一巡する前までの状態。
麻雀用語辞典へ - 空テン(カラテン)
- アガり牌が場にすべて見えていたり自分が使用しているなどで、牌山に1枚もないテンパイのこと。
麻雀用語辞典へ - チー聴(チーテン)
- チー(副露)を宣言して取得した牌でテンパイの状態になること。
麻雀用語辞典へ - 筋(スジ)
- あと1枚揃えば 順子(シュンツ) が完成する2枚組を塔子(ターツ)と言い、この 塔子 の 両面待ち(リャンメンマチ) となる両端の待ち牌のことを筋と言う。つまり筋は両面待ちのこと。例えば、手牌に、[ 4・5 ]がある場合においての[ 3-6 ]待ちなどである。全部で6筋ある。
[ 2・3 ]に対しての[ 1-4 ]
[ 3・4 ]に対しての[ 2-5 ]
[ 4・5 ]に対しての[ 3-6 ]
[ 5・6 ]に対しての[ 4-7 ]
[ 6・7 ]に対しての[ 5-8 ]
[ 7・8 ]に対しての[ 6-9 ]
以上6筋
麻雀用語辞典へ - 表筋(オモテスジ)
- 他家(ターチャ) が 両面待ち(リャンメンマチ) をしている場合にフリテンルールにより安全とされる 牌 のことで、他家 の 捨牌 に[ 4 ]がある場合は[ 1-4 ][ 4-7 ]待ちはない、[ 5 ]がある場合は[ 2-5 ][ 5-8 ]待ちはない、[ 6 ]がある場合は、[ 3-6 ][ 6-9 ]待ちはない、とする考えのもと、
捨て牌[ 4 ]に対する筋[ 1-7 ]、捨て牌[ 5 ]に対する筋[ 2-8 ]、捨て牌[ 6 ]に対する筋[ 3-9 ]
が表筋の3筋である。
麻雀用語辞典へ - 中筋(ナカスジ)
- 他家(ターチャ) が 両面待ち(リャンメンマチ) をしている場合にフリテンルールにより安全とされる 牌 のことで、他家 の 捨牌 に[ 1・7 ]がある場合は[ 4 ]の待ちはない、[ 2・8 ]がある場合は[ 5 ]の待ちはない、[ 3・9 ]がある場合は、[ 6 ]の待ちはない、とする考えのもと、
捨て牌[ 1・7 ]に対する筋[ 4 ]、捨て牌[ 2・8 ]に対する筋[ 5 ]、捨て牌[ 3・9 ]に対する筋[ 6 ]
が中筋の3筋である。
麻雀用語辞典へ - 片筋(カタスジ)
- 他家(ターチャ) が 両面待ち(リャンメンマチ) をしている場合に片方のみの待ちに絡む 牌 のことで安全牌読みで使用される筋。他家 の 捨牌 に
[ 1 ]がある場合は[ 4 ]、
[ 2 ]がある場合は[ 5 ]、
[ 3 ]がある場合は[ 6 ]、
[ 7 ]がある場合は[ 4 ]、
[ 8 ]がある場合は[ 5 ]、
[ 9 ]がある場合は[ 6 ]
の筋のこと。
麻雀用語辞典へ - 裏筋(ウラスジ)
- ある捨て牌の隣の牌から成るスジのことで危険牌とされる。嵌張待ち(カンチャンマチ) から 両面待ち(リャンメンマチ) に切り替わる際などに起こり得るメカニズム。例えば、[ 4・6 ]の嵌張待ちで[ 7 ]をツモ し、[ 4 ]が切り出された場合、待ちは[ 5-8 ]となる。つまり、[ 5-8 ]は[ 4 ]の隣の牌である[ 5 ]から成る筋である。この考えのもと 裏筋 は全部で9種ある。
[ 1 ]が捨牌にある場合[ 2-5 ]、
[ 2 ]が捨牌にある場合[ 3-6 ]、
[ 3 ]が捨牌にある場合[ 4-7 ]、
[ 4 ]が捨牌にある場合[ 5-8 ]、
[ 5 ]が捨牌にある場合[ 1-4 ][ 6-9]、
[ 6 ]が捨牌にある場合[ 2-5 ]、
[ 7 ]が捨牌にある場合[ 3-6 ]、
[ 8 ]が捨牌にある場合[ 4-7 ]、
[ 9 ]が捨牌にある場合[ 5-8 ]。
麻雀用語辞典へ - 間四軒(アイダヨンケン)
- ただの裏筋ではなく、裏筋が2つ重なってさらに危険となっている状態。例えば、他家(ターチャ) の 捨牌 に、[ 1 ]と[ 6 ]がある場合、[ 1 ]の 裏筋 は[ 2-5 ]であり、[ 6 ]の裏筋も[ 2-5 ]であるので、[ 2-5 ]筋は 間四軒 となる。
麻雀用語辞典へ - スジを追う
- スジのメカニズムに従って安全と思われる牌を 打牌(ダハイ)する、または、 危険と思われる牌を打牌しないしないで ロン を避ける戦術。
麻雀用語辞典へ - オリる
- テンパイ者 や リーチ者 に対して、自分の 手牌 を揃えることより、他家 に ロン されないように安全な牌を捨てたり、危険牌の打牌(ダハイ)を避けたりすることを優先する守備の戦法。
麻雀用語辞典へ - ベタオリ
- テンパイ者 や リーチ者 に対して、完全に勝負を諦めて、現物(ゲンブツ) や 完全安全牌(カンゼンアンゼンハイ) を最優先で打牌(ダハイ)し、現物などがなければ、スジ追いによる安全牌や危険牌の推測によって ロン を極力回避し守備に徹する戦法。その際、自分の手牌が崩れても全く構わないとする。
麻雀用語辞典へ - ツッパる
- テンパイ者 や リーチ者 に対して、危険牌と思われる牌でも打牌(ダハイ)し、 手牌 を揃え アガる ことを優先する一打。
麻雀用語辞典へ - ゼンツッパ
- テンパイ者 や リーチ者 に対して、危険牌 を打牌(ダハイ)してでも自分の 手牌 を揃え アガる ことを最優先する戦法。=ゼンツとも言う。ゼンツッパの場合は、アガれるまで一貫して攻撃的な打牌(ダハイ)を貫く。
麻雀用語辞典へ - 回し打ち(マワシウチ)
- テンパイ者 や リーチ者 に対して、安全牌を打牌(ダハイ)し危険牌を避けて ロン を回避しつつ、自分の 手牌 を揃えて アガり を目指す戦法。
麻雀用語辞典へ - 合わせ打ち(アワセウチ)
- 自分の1つ前の人(上家:カミチャ)が 打牌 したのと同じ種類の牌を合わせ打つ守りの戦法。この牌は同巡内において完全安全牌となり、どのプレイヤーからもロンされない。
麻雀用語辞典へ - スジ追い
- スジのメカニズムに従って安全と思われる牌を 打牌(ダハイ)する、または、 危険と思われる牌を打牌しないしないで ロン を避ける戦術。
麻雀用語辞典へ - 壁
- 場に同じ種類の数牌(シューハイ)が4枚すべて見えていること。また、それにより 両面待ち に対応した安全牌の壁スジが出現し、その牌を打牌して ロン を回避する守備の戦法。
麻雀用語辞典へ - ノーチャンス
- 壁のこと。場に同じ種類の数牌(シューハイ)が4枚すべて見えていること。また、それにより 両面待ち に対応した安全牌の壁スジが出現し、その牌を打牌して ロン を回避する守備の戦法。
麻雀用語辞典へ - ワンチャンス
- 場に同じ種類の数牌(シューハイ)が3枚見えており、それにより 両面待ち に対応した安全牌の壁スジが出現し、その牌を打牌して ロン を回避する守備の戦法。ただ、残りの1枚で 両面待ち に構えているプレイヤーがいる可能性が残っている。
麻雀用語辞典へ - 現物(ゲンブツ)
- テンパイ者や立直(リーチ)者の捨て牌、鳴かれた牌、リーチ後の捨て牌のことで、対象のプレイヤーからは ロン されない牌。
麻雀用語辞典へ - 完全安全牌(カンゼンアンゼンハイ)
- プレイヤー全員の捨て牌にある牌で ロン される可能性が0%の牌。合わせ打ちの牌も完全安全牌であるが、同巡内に限る。
麻雀用語辞典へ - 生牌(ションパイ)
- すべてのプレイヤーの捨牌やドラ表示牌、副露牌すべてにおいて1枚も場に見えていない牌のこと。
麻雀用語辞典へ - 錯和(チョンボ)
- ルール違反やミスによる麻雀の反則行為のこと。チョンボにはいくつか種類があり、反則行為をしたプレイヤーはペナルティーとして罰符の支払いやアガり放棄などの罰則がある。
麻雀用語辞典へ - 罰符(バップ)
- ルール違反やミスによる麻雀の反則行為をした場合や、ノーテンの場合に支払う点数 又は、点棒のこと。
麻雀用語辞典へ - 包則(パオ)
- 役満(ヤクマン)を確定させるような行為をした場合に 罰符(バップ) を支払うルール。
麻雀用語辞典へ - タテチン
- 手役の1つである清一色(チンイーソー)を門前(メンゼン)で進行・アガること。
麻雀用語辞典へ - バカホン
- 混一色(ホンイツ)をドラや他の役などと組み合わせずホンイツのみの手で仕掛けたりアガったりすること。
麻雀用語辞典へ - スッタン
- 四暗刻(スーアンコウ)単騎(タンキ)待ちで和了すること。
麻雀用語辞典へ - 亜空間殺法(あくうかんさっぽう)
- 安藤満氏が提唱した麻雀ゲームの理論名。
麻雀用語辞典へ - オカルト麻雀
- 「ツキ」や「運」を基軸とした戦術であるオカルト的手法を基盤とする戦術論。アナログ麻雀などとも言う。
麻雀用語辞典へ - デジタル麻雀
- 「ツキ」や「運」を基軸とした戦術であるオカルト的手法を基盤とするオカルト麻雀に対して、抽象的思考を排除し牌効率を重視した戦術論。1990年に天野晴夫氏が提唱。小倉孝(オグラタカシ)氏 や 鈴木たろう氏 など若手のプロ雀士の戦術として取り入れられている。
麻雀用語辞典へ
待ち系用語
立直/テンパイ系用語
スジ系用語
戦術系用語
ペナルティー用語
役に関する用語
その他
関連タグ
皆さまのご感想、コメントなどお寄せください
コメント開閉






皆さまからのコメントと麻雀豆腐編集部からの返信!
錯和 の意味を教えてください。先日プロの動画で1人のプロの打牌後3人が顔を見ああせました、画面に錯和と表示され、-12000
が表示され、罰金のことかと思いましたが、正確には何でしょうか。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>錯和 の意味を教えてください。
こちらは「チョンボ」という意味になります。
チョンボしますと罰符を払ったり、成績からポイントをマイナスになったりしますので、-12000は罰符を同卓者に支払ったのかと思われます。
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。
同一局においてAの親が多稗でチョンボBの子がリーチで見逃しチョンボ2者がチョンボで流局しました
。AB 両者満貫支払いですがC者Ⅾ者で分配またAのチョンボはBCD3者でBのチョンボはACDで 分配 私はABはチョンボで分配受領権利がないと思いますが正式には対処方法御指導願います。珍しいことですが
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>正式には対処方法御指導願います。珍しいことですが
正式な対処方法というものはなく、お仲間内でどういう取り決めをされているかになります。
ですが一般的には、自分がチョンボをしたかどうかに関わらず他者の罰符を受け取る権利はあります。
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします
そのドラ!ロンッ!
客風牌対子・翻牌対子とは?
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>客風牌対子・翻牌対子とは?
客風牌対子はオタ風が対子という意味です。
翻牌対子とは三元牌および自風・場風の対子を指します。
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。
分かりやすくてとても勉強になった。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>分かりやすくてとても勉強になった。
そう言っていただけるととても光栄です!不明点などございましたらいつでもコメントくださいませ。
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。
自模牌→山,捨て牌のエリヤ→河 , 手牌や鳴いたメンツを置くエリヤのことを
何と言うのですか? 教えてください。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>手牌や鳴いたメンツを置くエリヤのことを何と言うのですか?
お調べしましたが特に名前はないようです。
今後とも麻雀豆腐をよろしくお願いいたします。
りゃんめん縛りとは
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>りゃんめん縛りとは
こちらの記事の用語の中には載っていないものですね。
私自身、リャンメン縛りという単語は聞いたことがありませんが、恐らくリャンメンでしか和了できないルール、ということです。
お役に立てますと幸いです。
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。
リャンハンシバリのまちがいではないでしょうか
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>リャンハンシバリのまちがいではないでしょうか
おっしゃる通り、「りゃんめん縛り」というルールがあるよりもどちらかと言えば「りゃんはん縛り」かと思われます。
用語集にはまだ掲載がありませんので記事にしたいと思います。
ご意見ありがとうございます!
今後とも当サイトをどうぞ宜しくお願い致します。
見たくもないのに自牌を見せびらかす奴がいます。「見せ牌」と言うのでしょうか?甚だ迷惑な事です。
その延長行為で危険牌を手牌の傍にポロッと晒し周囲の反応を見てから河に置きます。
こちらの反応次第では「まだ河に出してない」と言い、違う牌に変える輩がいます。
これは「ペナルティ」?「マナー違反」?「問題無し」?
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>これは「ペナルティ」?「マナー違反」?「問題無し」?
お店でのことでしたらお店に裁定を仰いでください。
お仲間内のことでしたら見せ牌を禁止にすれば問題は解決されます。
お役に立てますと幸いです。
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。
役満の種類を教えてください。かたちも教えてください。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>役満の種類を教えてください。かたちも教えてください。
役満の種類や形につきましては、下記の記事をご参考ください。
https://majandofu.com/mahjong-hands-simple
お役に立てましたら幸いです。
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。
だまてん(リーチなし)でピンフのみでふりこみました。4566待ちは、ピンフになりますか、
3はピンフ、6は頭待ちとなると思います。3で振込ましたが、疑問がでました。よろしくおねがいします。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>だまてん(リーチなし)でピンフのみでふりこみました。4566待ちは、ピンフになりますか、
>3はピンフ、6は頭待ちとなると思います。3で振込ましたが、疑問がでました。よろしくおねがいします。
こちらは6が頭で、36のリャンメン待ちと捉えることができますので平和になります。
6の頭待ちの解釈は可能ですが、それだと役なしなのであがれませんし、そもそも麻雀は高点法といい、
常に最も高くなるよう計算しなくてはなりません。
お役に立てますと幸いです。
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。
誤字報告です。
>親 以外の 南家(ナンチャ) 西家(シャーチャ) 北家(ペーンチャ) のこと。
→北家(ペー【】チャ) のこと。
>最終局(オーラス)で和了ったにも関わらず
→かかわらず(拘らず)
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>誤字報告です。
申し訳ありません、該当箇所を修正致しました。
いつも誠にありがとうございます!m(__)m
コンテンツに間違いないようより一層の注意を払い、ご利用していただけるユーザー様と共に麻雀豆腐も成長していけるように努力致します。
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します。
マナーかルールか解りませんが質問です
リーチの宣言タイミングについて「通ればリーチ」はいいにしても打牌後鳴きが入らない事を確認してからリーチ宣言はマナー違反ではないか。そのような場合はリーチは取り消しとなる?
(罰則でも有るでしょうか)
鳴くか鳴かないか「ちょっと待って!」どの程度まで許される行為でしょうか。自分の自摸番の時は許されるとしても下家、対面の捨て牌に「ちょっと待って」。考慮の後「やめとく!」は無いでしょう。マナーとしたら如何なものでしょうか。(この場合の罰則は有り、無し?)
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>リーチの宣言タイミングについて「通ればリーチ」はいいにしても打牌後鳴きが入らない事を確認してからリーチ宣言はマナー違反ではないか。そのような場合はリーチは取り消しとなる?
リーチの手順は、「リーチ」と発声→牌を横向きにして捨てる→リーチ棒(1000点棒)を出します。
自身がリーチを宣言し打牌した後はリーチの取り消しは出来ず、他家の鳴きが入らない事を確認してからリーチは出来ません。
リーチ宣言後の1巡以内にポンやチーがあった場合は一発は消え、次巡の牌を横にするルールとなりますm(__)m
>鳴くか鳴かないか「ちょっと待って!」どの程度まで許される行為でしょうか。
鳴くか鳴かないか関しても、「ちょっと待って!」「やっぱやめた!」などの発言に対しては、誤ポンや誤チー扱いとなったり、その牌でロンが出来なくなるというルールもあります。
罰則やどの程度まで許されるかにつきましてはその場の取り決めによって異なりますが、上記のような行為は避けるよう気を付けたいですね(>_<) はっきりとした回答が出来ず申し訳ありません。 今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します!
丁寧な回答頂き有難うございます。親しい仲間での麻雀なので「まあいいじゃない!」で済ませています。でも勝負事です。「基本、ルールはこうです」と説明し、今後も楽しく麻雀したいと思います。
麻雀豆腐編集部です。
麻雀豆腐サイトのご利用誠にありがとうございます!
>親しい仲間での麻雀なので「まあいいじゃない!」で済ませています。でも勝負事です。「基本、ルールはこうです」と説明し、今後も楽しく麻雀したいと思います。
そうですね!
ユーザー様の仰る通り、真剣に、気持ちよく麻雀を楽しめることが一番だと思います(^^)
麻雀のルールは様々で、このルールが正解!とは言えない部分もたくさんありますが、だからこそ奥深く、一緒に麻雀を楽しむメンバーと共有していきたいですね。
貴重なご意見、コメントをいただきありがとうございます!
今後とも麻雀豆腐を宜しくお願い致します!