平澤元気 麻雀 鳴きの教科書【初心者向け/おすすめ麻雀本】
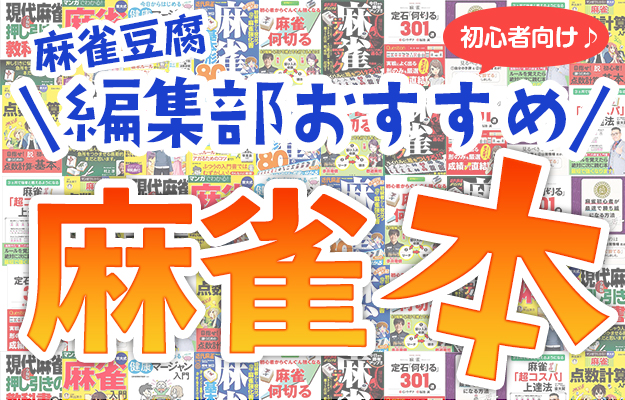
かつて全日本麻雀協会に所属し、現在はフリープロとしてYouTube番組の製作や戦術本の執筆で活動する平澤元気プロが書いた、鳴きの教科書です。鳴きに関する技術に触れた戦術本は存在しますが、どれも中級者以上向けで難解なものが多く初心者が読むにはハードルが高いものとなっていました。
しかし本書は副露の基礎から丁寧に解説されているので、ルールと牌効率を覚えてこれから強くなりたいという初級者の方が学ぶにはもってこいの内容となっています。
麻雀 鳴きの教科書
副露判断の基礎を学ぶならこの本!
- 麻雀豆腐編集部
おすすめ麻雀本! 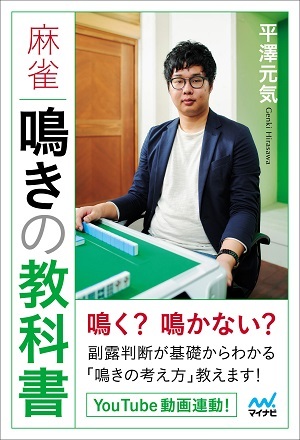
初級中級戦術
- おススメ度
- 難易度レベル
タイトル
麻雀 鳴きの教科書
内容紹介
アガリ回数を劇的に増やす!鳴きの技術
本書では副露に関するテーマを
(1)そうは言ってもこれは確実に鳴くべき/鳴くべきじゃない、と言えるもの
(2)強者でも意見が分かれそうなものに分類し、まずは初級者向けの内容「副露の基本」として(1)を解説しています。
(2)に関しては無理に答えを断言することはせず、「こんな場況なら鳴くべき」「こんなルールならスルーすべき」という風に、答えを出す力が身につけられるような考え方のポイントを解説しています。出典:麻雀 鳴きの教科書
著者について
平澤元気プロ
人気麻雀YouTuberとして活躍する麻雀クリエイター。
2016年に天鳳の最高段位十段に到達したことで戦術本を初出版。2020年まで全日本麻雀協会で競技麻雀プロとして活動するが退会しフリープロに転身する。
現在は麻雀戦術を解説するYouTubeチャンネル「平澤元気 麻雀ch.from雀劇tv」は登録者数10万人を超える人気コンテンツを運用する他、多数の戦術本を出版。
「麻雀 鳴きの教科書」を読もう!
ルールを覚えて、牌効率を覚えて、基本的な戦術を覚えて・・・となると、そろそろ手を出したくなるのが「副露の技術」ではないでしょうか。
副露に特化した戦術本って、意外と少ないです。あっても中級者以上向けでフリーで勝つことを目的とした内容だったりして、初級者にはハードルが高かったり・・・。
そんな初級者の方にオススメなのがこの麻雀 鳴きの教科書です!
牌効率の技術アップとしては何切る問題が主流ですが、副露の技術アップには副露の状況判断が鍵となるので主にその考え方が解説されています。
教科書の最後には練習問題が付いているのでおさらいもできますし、本書の補足としてYouTube動画の案内もあり、至れり尽くせりの内容となっています。
第1章 副露の概念論
副露の技術を身につける前に、この章でまず「副露を考える上で注意したいこと」について解説されています。
副露判断は強者によっても考え方によりバラバラであるため、正解を求めるのが難しい、と平澤プロは考えます。
なので、「これは鳴くのが正解」「これは鳴いたら絶対ダメ」といった何鳴く問題が出るわけでなく、「考え方を解説する」ことで副露判断の実力アップを図ることが本書の目的なのだということを理解して次の章以降に臨みましょう!
第2章 鳴きの基本編
第1章を読むと、「副露って何だかメチャクチャ難しそうだな、、」と不安になるかもしれません(笑)。
大丈夫です、第2章は「これを鳴いたら明確に損!」「これは絶対に鳴いた方が良い!」という基本について触れられています。
「愚形のポンテンチーテンは逃すな」「満貫見えれば全力疾走」など、9つのテーマが設けられ、1テーマ1牌姿を使って副露の判断の考え方について深堀りされています。
ここがイイね!
例えばテーマで挙げられた最初の牌姿が「鳴いてはいけない」場合はその理由を、ではどんな牌姿であれば「鳴くべきなのか」の説明もあり、最後にポイントがまとめられているので頭に入りやすく、実戦でも応用しやすいです!
第3章 微差何鳴く編
この章では強者であっても競技/フリーなどのフィールドや打ち方のスタイルによって副露判断が変わる微差の牌姿が扱われています。
第1章でも触れられた通り、副露は正解を求めるのが難しいテーマですが、メリット・デメリットを言語化し自分の打つフィールドや状況に合わせて副露の選択ができるようになることを目指します。
例えば東1局なら鳴かないが、オーラスアガりトップなら鳴くだろうか?といった思考の言語化ができるようになると自然と副露判断の精度が上がるでしょう。
- 初心者脱出のポイント
- 実戦で副露判断に迷った場合は牌姿を残し、何故迷ったのか、どういう状況なら絶対に鳴きたいか/鳴きたくないか、メリットやデメリットなど思いつくあらゆる内容を書き出すことで、思考を言語化する練習をしましょう。
第4章 状況判断編
第3章では「微差何鳴く」を取り扱いましたが、他家の捨て牌や点棒状況といった情報があると、微差の「鳴く」「鳴かない」が精度高く判断できそうですよね。
本章ではその「微差」の問題に対処するための状況判断について解説されています。
「ゲームの進度に対する点棒状況」、「南2局〜南3局における副露基準」、「相対速度」、「上家の捨て牌」、「山読みの精度」といった構成で、牌姿に対して点棒状況やゲームの進度が挙げられ、鳴く/鳴かないの考え方に対する説明が記されています。
- 初心者脱出のポイント
- 点数状況を加味した副露判断というのはかなり難しく、直撃・ツモアガり・他家同士の点差も素早く計算できる必要があります。初級者の方ですとここら辺で頭がパンクするかもしれません。
ですが、状況を判断できてこそ初めて適切な副露ができるわけで、避けては通れない問題なので、もし点棒状況や捨て牌・速度読みがまだ不完全であると感じる場合はまずそこから取り組むと本書の解説を最大限に活かせるかと思われます。
第5章 鳴きの小ワザ編
本書での重要なポイントは第3・4章となり、ここがマスターできれば副露判断は90%完成されたと言っても過言ではないでしょう。
第5章では、知っていると少し得をする細かなテクニックについて解説されています。
アガりにはつながりませんが、形式テンパイを取るための副露基準やカンチャンを3面張に変える鳴き方などが紹介されています。
小技を入れることでテンパイ料分加点したり、テンパイ速度を加速させる事ができるので、直接アガりに繋がらない技術も積極的に磨いていきましょう!
まとめ
本書は副露の判断基準における考え方を身につける教科書です。
副露は強者であっても状況により考え方がバラバラであるため、本書では副露判断の解説を行うことによって読者の実力アップを図っています。とは言え、絶対に鳴いたほうが良い・鳴かない方が良いというものは存在するので基本的な事は第2章でまとめられています。
そして、微差の何鳴く、それを判断するための技術については第3章・第4章に記されています。ここを抑えると副露に関しては90%マスターしたと言っても過言ではありません!
第5章では形式テンパイの副露判断やブラフなど、副露の小技について解説されています。
最後まで読むと練習問題がついているので、理解できたかおさらいできます。
さらに、本書は各項目を初心者の人でも分かりすいように説明されたYouTube動画へのリンクが付いています。本と動画で実力アップを加速させることができる、良書なので副露をマスターしたい方は是非手にとってみてください♪
著作紹介
- タイトル:麻雀 鳴きの教科書
- 平澤元気(著)
- 出版社:マイナビ出版
- 発売日:2019/12/23
- ページ数:224ページ






皆さまのご感想、コメントなどお寄せください